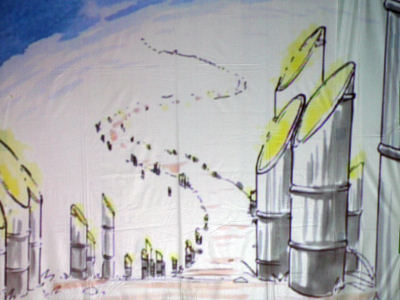真名長者(まなのちょうじゃ)伝説より 「うすき竹宵」の由来
「うすき竹宵」は都から玉絵箱と供に帰ってきた般若姫の御霊の里帰りを表現したものです。

臼杵の誇りである「臼杵石仏」は炭焼小五郎が奈良の都から来た玉津姫と結婚した事で
後に真名長者と呼ばれる大金持ちになり この真名長者が造ったと伝えられています。


真名長者は名を炭焼小五郎といい、その妻は玉津姫と言いました。
また、二人のあいだに産まれた娘は般若姫と言いその美しさと気品は世間の評判となっていました。


(上の般若姫の大きな像は豊後大野市の内山観音の近くにあります)
般若姫の噂を聞いた時の朝廷は、姫を妃として都へ差し出すように使者を遣わしますが、
長者は一人娘と言う理由でこれを拒み、代わりに姫の姿を書き写した「玉絵箱」を献上しました。
ところが、献上された玉絵箱を見て恋に落ちた若者がおりました。

それは、後の用明天皇、当時は橘の豊日の皇子でした。皇子は般若姫に逢うため草深い臼杵に下り、
牛飼いに身をやつして長者のもとに身を寄せ、やがて般若姫と結ばれました。

しばらく幸せな時を過ごしますが、皇子は朝廷に呼び戻され懐妊していた般若姫を残して
都へと帰っていきました。
しばらくして般若姫は玉絵姫と言うかわいい女の子を出産します。
そして、般若姫は産まれたばかりの玉絵姫を残し、皇子の待つ都を目指して臼杵の港から船出します。
ところが、途中嵐に遭い、帰らぬ人となりました。悲しんだ長者夫婦は、
般若姫の供養のため玉絵箱の里帰りを願い出て、朝廷もこれを許されました。

亡き般若姫の姿を描いた「玉絵箱」は長者夫妻にとっては娘。
玉絵姫にとっては母そのものだったのでした。

暮れ早い秋の陽はとっぷりと暮れ、里人たちは竹に明かりを灯し暗くなった夜道を明るくしました。

このうすき竹宵の般若姫行列は長者夫妻と玉絵姫が待つここ臼杵へ
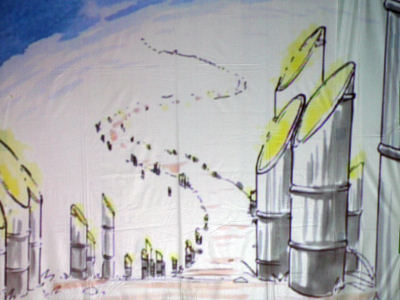
上のイラストは竹で作られたシアターで上映していた物語画面を撮影して使いました
平成18年のうすき竹宵公式ホームページもご覧ください。


| 真名野長者と般若姫 伝説 |
いまからおよそ千四百年ほどむかし。豊後の国大野郡三重の山里に、藤治という若者がおったそうな。藤治は三さいで父に、七さいで母にも死にわかれ、みなしごになってしもうての。おなじ村の玉田の里の炭焼き又五郎にひきとられてそだてられたんじゃと。
藤治は又五郎を父としんじて、炭焼きのてつだいにせいをだしておったが、藤治が十一さいになってほどなく、又五郎は八十一さいでこの世をさったて。藤治は、又五郎のあとをついでますます炭焼きにせいをだし、炭焼小五郎とよばれるようになったのだと。
そのころ奈良の都に、久我大臣のむすめで玉津姫といううつくしい姫がおった。ところが、どういうわけか、あるときにわかに、そのうつくしい顔に、みにくいあざがしょうじてしもうた。このため、姫には夫となる人がなかなかきまらん。
そこで玉津姫は、(夫となる人にはやくめぐりあえますように……。)と、大和の国、三輪の神さまに、まい夜おまいりをつづけておった。
すると、二十一日めの満願の夜、にわかに大雨となって、一歩もうごけなくなってしもうた。姫がしばらく拝殿に雨やどりをしていると、いつしかふっとねむ気がさして、そのゆめの中に、三輪の神さまがあらわれたて。
「姫よ、あなたの夫となる人は、豊後の国、三重の玉田の里におる炭焼小五郎というものじゃ。この若者と夫婦のちぎりをむすぶなら、ゆくすえしあわせになれるであろう。」
神さまは、おごそかにつげ、すうつと立ちさったんじゃと。
ゆめからさめた姫は、すぐさまやかたにかえり、旅のしたくにとりかかったて。
あけて十六さいの春二月、姫はひとりひそかに都をぬけだし、豊後の国、三重の山里へ旅だったのじゃと。
野をこえ、山をこえ、姫は、はるばる三重の山里にたどりついたそうな。
しかし、日はとっぶりとくれてしまい、道らしい道とてもなく、姫はとほうにくれてしまった。
すると、くらやみの中から、白髪の老人が姫のまえにあらわれたんじゃ。姫が、「わたしは都のものですが、この山里に炭焼小五郎という人がおるときいて、たずねてまいりました。あなたは炭焼小五郎という人をごぞんじないでしょうか。」と、たずねると、「小五郎なら、よく知っておる。だが、もう日もくれてしもうた。今夜は、わしの家にとまっていくがよい。夜があけたら、あわせてあげよう。」といい、老人はじぶんのやかたへ姫をあんないしたんじゃと。
老人のやかたの庭には、たくさんの花がいまをさかりとさきみだれ、そのおくのほうに大きな家がたっておった。
姫は、おおくの女中たちにでむかえられ、へやにとおされたて。そのへやは金銀でかざられておって、目もくらむばかりのつくりであったそうじや。女中たちは、みな姫にしんせつをつくし、「金亀ケ淵というところで顔をあらえば、もとのうつくしいお顔になりましょう。」と、おしえてくれたそうな。
だが、朝になって姫がふと目ざめてみると、やかたなどかげもかたちもなく、きのう老人とあった山の中で姫は、松の根をまくらにねていたのであった。かたわらを見ると、白髪の老人が、きのうのままのすがたでねておる。
「これはすっかりねむってしもうた。どれ、ごあんないいたそう。」
ねむりからさめた老人は、姫のさきに立ってあるきだしたて。
しばらくいくと、一けんのみすばらしいシバの小屋があったそうな。老人は、「やがて、この小屋の主人もかえってくるじゃろう。しばらくここでおまちなされ。」
というと、かきけすようにすがたが見えなくなってしもうた。
姫が小屋でまっていると、ほどなく、手も足も顔もまっ黒によごれ、ぼろを身にまとった若者が、かえってきたんじゃと。
「もしや、あなたは炭焼小五郎さまではございませんか。」
と、たずねると、若者は姫の顔をまじまじと見つめながら、「いかにも炭焼小五郎じゃが、おまえさまはいったい……。」と、いうたて。やはり神さまの引き合わせだったのじゃろ。
さきほどの老人こそ、その神さまだったに違いない、喜んだ姫は、「わたしは都からはるばる、この三重の里まで小五郎さまをたずねてやってまいりました。そのわけは、大和の国、三輪の神さまのおつげで……。」と、ことのなりゆきをはなしたんじゃと。その話をきいて、小五郎はたまげてしまい、「たいへんありがたいお話じゃが、わたしはこのとおり貧乏で、わずかの蓄えもありません。ひとりでさえ、暮らしていくのがやっとの身、このうえあなたを養っていくことなど、とてもできません……。」
と、ことわったが、「貧乏をしょうちのうえでの頼みです。どうか、おそばにおいてください。」姫は、目に涙をうかべて頼んだて。
小五郎は、さすがに断りきれず、ふたりで小屋にすむようになったんじゃが、ろくに食べものも着る物もない。そこで姫は、もってきた黄金をとりだし、小五郎にたのんだのだと。「これで、なにか食べものを買ってきてください。」小五郎は、はてな……という顔をしながらも、小屋をでていきよったが、まもなく手ぶらでもどってきたんじゃと。姫がふしぎにおもって、「いったい、どうしたのですか。」と、たずねると、「この下の淵にたくさんのカモがいたので、あなたがくれた石をなげつけたのじゃが、うまくあたらんもんじゃのう。とりそこのうてしもうた。」 小五郎は、なんとも残念そうにこたえたんじゃと。
姫は、黄金のねうちを知らない小五郎におどろいて、「あれは、ただの石ではありません。黄金という大事なものなのです。黄金があれば、食べ物でもきものでも、なんでも買えるのですよ。」と、おしえたんじゃと、すると小五郎は、わらいながら、「あんなもの、わたしが炭を焼いている窯のまわりや、カモのいた下の淵にいけば、いくらでんある。」と、いうた。姫は、またまたおどろいて、「それなら、わたしをその淵へつれていってください。」
と頼んだ。ふたりで下の淵までいってみるとたくさんの黄金が、ピカピカかがやいておった。姫が淵をながめておると、淵の水がうずまいて、金色のカメがうきあがってきたて。さては昨夜のゆめにきいた金亀ケ淵というのは、この淵のことではあるまいか。姫は淵におりて顔をあらったのだと。すると、たちまち姫のみにくいあざがきえ、見ちがえるほどうつくしゆうなったんじゃ。
それからふたりは、下の淵や炭焼きがまのあたりで黄金をひろいあつめてな。たいそうな金もちになったんじゃと。そして、いつしか真名野長者とよばれるようになったそうじや。
真名野長者となってから、小五郎は、ふかく仏教を信心するようになっての。唐(いまの中国)の天台山に黄金三万両をおくったりした。天台山では、百済の僧である蓮城法師に薬師、観音の二体の尊像をもたせ、このおかえしのため日本にわたらせたそうじや。
長者は蓮城をむかえ、尊像をまつる寺を建立した。これがいまの三重町内山にある蓮城寺、つまり内山観音であるとつたえられておる。
長者夫妻ほ、そのうち天女のようなうつくしい女児をもうけ、般若姫と名づけた。般若姫は内山観音のもうし子といわれ、いまも奥の院につたわる一寸八分の観音像は、そのまもり本尊であるといわれている。
さて、年がたつにつれて、般若姫のうつくしさは、とおく都にまできこえるようになったて。そのころ、欽明天皇の皇子橘豊日皇子(のちの用明天皇)は十六さいになっていたが、まだ、お妃がなかった。そこで、勅使(天皇のつかい)が、はるばる豊後の国、三重の里までくだってのう、「ぜひ豊日皇子のおきさきになってほしい。」と、もうしいれたが、「般若姫は、内山観音のもうし子であるから……。」と、長者は、ききいれなかったんじゃと。
勅使からこのことをきいた皇子は、すがたをかえて、ひそかに都をはなれ、豊後の国にやってくると、長者のやかたに奉公して、はたらきはじめたんじゃ。
皇子は、名も山路とかえてのう。草かりや牛かいにあせをながして、じつにようはたらいたそうな。そのうえ、なんともかしこい。長者はいつしか、山路がすっかり気にいったて。般若姫もいつとはなく山路をしたうようになっておった。
そこで長者は、山路を姫のむこにすることにした。
山路をむこにむかえ、姫も長者もまんぞくなまい日をおくっておったが、ある日のこと、とつぜん山路のもとへ都から勅使がやってきた。おどろく姫と長者夫妻にむかって、山路は、つらそうにうちあけた。
「じつは、わたしは橘豊日皇子です。父天皇からのよびだしで、いそぎ都へかえらねばなりません。ながいあいだ、いろいろとお世話になりました。」
長者夫妻は、あらためておどろいたが、このとき、般若姫はすでに身ごもっておったんじゃ。皇子はわかれにあたって、「姫よ。生まれた子どもが男なら、都へつれてのぼりなさい。もし女なら、長者の世つぎとしてのこし、姫ひとりで都へのぼりなさい。」と、いいのこしたそうじや。
般若姫は、やがて子どもを生んだが、それは女の子であった。姫は皇子とのやくそくどおり、ひとりで都へのぼることになり、臼杵の港から船出したのだと。長者はちかくの山にのぼり、いつまでも姫の船を見おくったて。この山が、いまの姫岳であるといわれておる。
だが、姫の船は、周防灘で大あらしにあってな。姫は、ついに帰らぬ人となったんじゃ。ときに十九さいであったそうな。
姫をうしなった長者夫妻のなげきは、たとえようもなくてのう。悲しみにしずんでおった。
ある日、長者は蓮城法師から、天竺にあるという祇園精舎の話をきいたんじゃと。
(人の命は、かぎりあるもの。できることなら、精舎のすがたを豊後の地にうつし、般若姫の供養もしたい。)
こうかんがえた長者は、石の仏のすがたを彫りあげようとねがったて。そこで、いまの臼杵市深田の里に満月寺がつくられ、岸壁に仏のすがたがきざまれていったんじゃ。だが、岩はかたく、岩のそこから男女のかなしげななき声ももれてくるようで、なかなか彫りあげることができんでおった。そうしたおり、東の方から見かけたことのない坊さんがあらわれてのう。ふしぎな術をもって工事をたすけ、たちまちにして石仏をつくりあげたんじゃと。
これがいま、臼杵にのこる名だかい石仏群じゃ。長者は、九十七さいでこの世をさり、玉津姫は九十一さいでねむりについたそうじや。墓とつたえられるものが内山観音にあり、ふたりの像といわれるものが、臼杵石仏のちかくにのこされておる。
偕成社発行の「大分県の民話」より
|